ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』感想
■糞の話
市川功『ピアジェ思想入門 ―発生知の開拓―』P48
清潔さを求める文化的な営みにおいても、衛生的な配慮というのはあとから考えだされた根拠づけにすぎない。こうした配慮は、衛生という観念が生まれる前から存在していたものであり、社会的な要素を含んでいるのは間違いのないところである。清潔さが追求されるようになるのは、排泄物が不快なものとして知覚されるようになり、それを除去しようという強い衝動が発生してからのことである。幼年時代にはこのようなことがなかったのは、誰もが知っていることである。子どもは排泄物をみても嫌悪を感じることはなく、排出された自分の身体の一部とみなして大切にするのである
- 裕福な家庭に家政婦(ないし本来その家の者たちが行うべきことのアウトソーサー)が入り込み、家庭内の権力秩序を撹乱すること
- 邸宅の階層ごとに、経済的な上部構造/下部構造の機能分化がされ、その間をつなぐ階段が象徴的に使われること
映画史のなかには、けっして数こそ多くないが、一連の自然主義者たちが存在している。ジル・ドゥルーズによれば、こうした監督の特徴とは、隔離された場所に小世界を創造し、そのなかで悪夢幻に苛まれていく人間関係をリアリストとして観察することにある。強い閉鎖性を帯びた空間のなかで、善と悪、富める者と貧しい者、主人と奴隷の対決が、いかなる監督よりも残酷で暴力的なかたちで描かれる。『ケリー女王』の沼地、『皆殺しの天使』や『召使』のお屋敷、『最後の晩餐』の田舎の邸宅を、思い出していただきたい。本来の世界は終末にむかって傾斜を見せ、それに逆らうことはできない。あらゆる救済の可能性は絶たれており、人間は堕落していくばかりだ。こうした自然主義者の映像にあってもっとも重要なのは「衝撃の映像」であると、ドゥルーズはいう。衝撃の対象としてのフェティシズムと倒錯。人間はもやは人間としてではなく、あらゆる希望を絶たれた昆虫のように描かれることになる。
■結び
TOHOシネマズ日比谷で鑑賞
『永野と高城。Vol.3』感想
『永野と高城。Vol.3』全6公演のうち、2019年10月26日(土)昼の部を見てきた。
賛辞の意を込めて「本当に酷い」コントばかりだったという話と、このお笑いライブは「美しかった」という話を書く。
1)本当に酷いコントばかりだった話
披露されたコントのタイトルを、記憶の限り書き出す。
※コントのタイトル一覧はオフィシャルから発表されておらず、俺のまだ湯気立つ記憶に依っているため、抜け漏れや不正確な表記は相当あると思う。
- イクラちゃんの霊に憑依された高城れに★
- 個人経営のパチンコ屋の独自ルールが全然客にウケていないところ★
- 草野球の監督の動きがサインじゃなくてただ可愛いだけだったところ
- グルメレポートを腕の力が弱いカメラマンが撮るところ
- 忘れんぼの芸人と優しいファン
- 犬人間をやめさせろ!★
- ステーキが早く食べたくて早歩きでステーキハウスへ向かう家族
- れにちゃんもうやめようよ★
- 人類史上初!スズキ エブリイになれた人
- ももクロのコンサートを仮病で休んだ高城れにが自分の価値を客席へ確かめにいくところ★
- 関係者席にクワバタオハラを見つけた大阪の歌手(今回のイベントテーマソング『ユーアノッアローン』の披露およびフリートークを前置きにして)
- かけると陽気になるサングラス
- 宗教の隣に猫カフェができたところ
- 公園のベンチをThe Diand FourのMVのステップで去っていく二人
- れにちゃんが去り際だけ礼儀正しくなるので寂しくなるところ★
どのコントも時に涙を流すほど笑ったが、個人的に、特に好きだったコントに星印を振った。
それらの感想を書いていく。
『イクラちゃんの霊に憑依された高城れに』
タイトルのとおり、れにちゃんがイクラちゃんの霊に憑依されている。
チャーン、ハーイ、バァブーとしか喋らない言語習得前の児童と化している。
このコントの底に敷かれているのはサザエさんと、ウィリアム・フリードキン『エクソシスト』である。
というか『エクソシスト』のほうが基底にあり、上モノの悪魔だけをイクラちゃんに差し替えたコントと言ってよい。
イクラちゃんはここでは悪魔なので(イクラちゃんが悪魔って?)、れにちゃんはチャーン、ハーイ、バァブーと言いながら、さまざまな悪事を行う。
このとき「ももクロの高城れににわざわざやらせる悪事」が酷い。
ガスコンロのつまみを緩く回し、ガス漏れを起こさせる。
親の財布から万札を抜き取り、破って捨てる(日本銀行券を破損させる)。
皿を割る(というか、ファンで埋め尽くされた客席に投げつける)。
高城れにとイクラちゃんという芸能界とアニメ界の双璧をなす無垢な存在にやらせる悪事の一つ一つが「それはふつうにやめろよ」な質感に満ちている。
最終的に神父である永野が(『エクソシスト』の展開同様に)れにちゃんに取り憑いたイクラちゃんの霊を自らに転移させ、悪魔に理性・身体を乗っ取られる前に、絶叫しながら2階の窓を突き破り、自殺する。
驚きをもって爆笑した。
この世界に、「イクラちゃんの霊を殺す」のがオチのコントが存在したということに。
『個人経営のパチンコ屋の独自ルールが全然客にウケていないところ』
永野やエキストラ一同がパチンコを興じている中、店員のれにちゃんがマイクで「立て」「座れ」「前川清(のモノマネをせよ)」という指示を繰り返す。
客たちは、この指示に従わないといけないという独自ルールを知った上で(それでもパチンコがやりたくて)店の門をくぐっている以上、渋々指示に従うが、それは衆愚であると気づいた永野が抵抗する。
「立て」と言われたら座り、「座れ」と言われたら立つ。逆のことをする。
ほかの客たちも永野に倣うと、誰もれにちゃんのマイクに従うものはいなくなる。
「立て!」「座れ!」が虚しく空振りを続けるうち、れにちゃんはその場に座り込んで、泣き出す。
泣かすつもりはなかった一同は、慌ててれにちゃんを慰めようと囲むと、その場に大きな煙がボワッと立ち込める。
煙が晴れたとき、中心に立つれにちゃんの頭には一枚の葉っぱが乗っている。
このコントもオチが酷い。
永野「狸の仕業だったのか!」
暗転。
『犬人間をやめさせろ!』
永野が公園を歩いていると、向かい側かられにちゃんが、リードでつながれた犬人間(四つん這いで犬歩きをした人間)を散歩させながら、笑顔で現れる。
コント冒頭、その絵が視界に飛び込んできた時点で、下顎が吹っ飛ぶような爆笑をした。
このコントは、「ももいろクローバーZは人権意識が薄い」という並行世界をえがいている。
永野「あれ?ももクロの、高城れにさん、ですよね?」
高城「はい!」
永野「何してるんですか?」
高城「(街中で話しかけてきたファンに”神対応”するような眩しい笑顔で)お散歩です!」
永野が問い詰めると、犬人間自身はれにちゃんと合意の下でその関係を結んでいることを、力強く「ワン!」と答えてくれる。
それであれば第三者が口を出すことではないか…と、永野はそのままれにちゃんと犬人間が去っていくのを見送る。
が、冷静になる。あんなことは人道にもとる。やめさせなければ!と思い、追いかけようとした瞬間、むしろ舞台袖の反対側かられにちゃんが戻ってきた。
リードでつないだ犬人間が3匹に増えている。
助けて。
永野「ももクロの、他のメンバーが知ったら、大変なことになりますよ」
高城「はあ!?他のメンバーはもっと飼ってるし!(夏菜子ちゃんは静岡と仕事現場で10匹ずつ飼っている(=夏菜子ちゃんの場合、実家の家族も協力している))」
永野「ももクロのファンの人たちが知ったら、大変なことになりますよ」
高城「はあ!?(客席を向いて)むしろファンの人たちこそ、こうなりたいよね?????」
観客一同「オーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」
高城「(不機嫌そうに)”オーーーーーーーー”じゃないでしょ!!みんなは、”犬”なんだから、"ワンワン"でしょ?????????」
観客一同「ワンワン!!!」
前提を確かめると、『永野と高城。』にはまず、お笑いのライブにももクロというモンスターグループのアイドルが出るために、そのアイドルのファンが客席を埋め尽くすというお笑い的には(いまさら誰も問題にはしないけど)そこそこ愁眉な事態がある。
このコントは、そうした事態を積極的に活用している。
つまりファンたちは犬である。そして「ライブはファンのみんなと一緒に作り出す」ものである。
ファンたちが「ワンワン!」と応えるとき、彼らに不謹慎な笑いに貢献しようという(そんなに高度な論理操作を要する)意図は一切ない。
愛するアイドルに何か求められたら、無批判で「是」で応じるという彼らにとって極めて一般的なコードを発動させているに過ぎない。エンターキーを押したら改行される程度の事象である。
『永野と高城。』は、その開催を遠く知るお笑い好きの人々が思うであろう「アイドルが混じることで、お笑い要素が薄まる」事態とは無縁である。逆である。
犬人間という属性が客席のファンたちにも波及する「ワンワン!」というコールアンドレスポンスが、「お笑い」というフレームを超えて狂っているために、このコントが成立する。
めちゃくちゃ笑った。
『れにちゃんもうやめようよ』
これは『永野と高城。Vol.2』に第一作を持つコントである。
れにちゃんが防弾チョッキとピストルを入手してきて、永野に「撃って~」とおねだりする。それを繰り返すだけのコントで、個人的には『Vol.2』で一番好きだった。
(後に『ももクロchan』#464に出演した永野も、これが『Vol.2』で一番ヤバかったよね、と語っていて嬉しかった)
よって、永野がこのタイトルを読み上げた瞬間「またやるのかよ(何度もやれるフォーマットじゃないだろ)」という事実にまず爆笑した。
れにちゃんが防弾チョッキとピストルを「川越のそっちの筋の人」から入手してくる。
『Vol.2』同様、れにちゃんが防弾チョッキをまとった上体を少し傾けて、無邪気な笑顔で「買っちゃった」と言うことがすでにオチ級の爆発力を持っている。
前回とは逆に、防弾チョッキを永野に着せ替え、自分がピストルを持って「撃たせて~」とせがむ。
媚態に負けた永野がデレつきながら承諾するが、いざ腹部を撃たれ、銃弾一発分の鈍痛に襲われると、地面に横たわりながら「あーーーーーーーーーーーー!!!!!」と叫ぶ。そして、当たり前のように一緒に舞台に立っているけどよく考えたら20歳年下のれにちゃんに、あらためて「この・・・・・・・・ガキが!!!!!」と叫ぶのが最高におもしろい。
『ももクロのコンサートを仮病で休んだ高城れにが自分の価値を客席へ確かめにいくところ』
ももクロのファンだから言うが、タイトルが酷い。
コンサートの客席に現れたれにちゃんは、黒い覆面をかぶり、”高城れに以外にめちゃくちゃ厳しい厄介客”のふりをして、公演中「高城れにのいないももクロなんかクソだ」と悪罵を吐き続ける。
すっかりテンションの落ちた周囲のファンたちを代表し、永野が「やめろよ!」と注意する。覆面を脱がされる。
周囲のファンたちに「れにちゃん・・・・・・・・!!!!」とバレても、れにちゃんはひるむことなくももクロの悪口を言い続け、最後に力強く「高城れにのいないももクロなんか、何の、価値も、ねえんだよ!!!」と叫んで、このコントが終わる
アフタートークで永野が語っていたが、このとき最前3列分ぐらいのファンたちが、静かに顎を引いてうつむき、落ち込んだ顔を見せるらしい(たまらない)。
もはや、台本の出来不出来が争点にはなりうるコントではない。
「ももクロへの罵倒を、高城れにの口から発させる」という行為性・事実性の一点に、このコントの強度が託されている。
個人的な昔話をするが、2014年に永野がいまはなき新宿・風林会館で単独ライブをしたとき、最後のトークで語られた内容をいまも印象深く憶えている。
乱暴に要約すれば、モグライダーの漫才はすばらしい。構成や伏線がなく、だいの大人二人がこの漫才のために練習している様がまったく目に浮かんでこない、からだと。
ひるがえせば、「背後に努力が見えてしまう漫才・コントにまったく興味が持てない」と、そのとき永野は語気を強めて言っていた。
永野は強固なアンチ・テクニックである。
そんな事実は永野のコントタイトルをずらりと眺めただけで、誰もが瞬時に分かることだと思う。
コントのシナリオ的完成度などをお笑いの問題から除外し、「うまい」「努力」を排した先にある強度の一点突破を貫いている。
その基本形を譲ることなく、自らのコントの磁場に高城れにを招聘する。
そのうえで、さらに「れにちゃんがいるからできること」を試行する。
それは昨日ツイートしたが、『Vol.2』の円盤に収録されたこんな場面からもよく伺える。
『永野と高城2』舞台裏映像だけど、永野がちゃんと『永野と高城』はお笑いなので(ほかのももクロの催しと違い)努力や達成感を快感にしてはいけないと言ってるの大変素晴らしいし、"かえって笑いづらくなる上手い演技"は『3』ではエキストラ含め完全に除去されてたと思う pic.twitter.com/ApqyMPtw27
— demio (@ganko_na_yogore) October 26, 2019
ももクロと永野がそれぞれ無関係にパラレルで好きな身分としては、こんなにも好きなものと好きなものがまったく互いの良さを摩滅せず、純然たる掛け算を起こして、笑えて、楽しいイベントはない。
れにちゃんが去り際だけ礼儀正しくなるので寂しくなるところ
これが『Vol.3』を締めくくる最後のコントである。
コントの導入は、ももクロ夏ライブが終演し『永野と高城。Vol.2』の共演者たち(永野以外は小劇場の役者たち)が関係者として、れにちゃんへ挨拶しにバックヤードを歩くところから始まる。
彼らはそれまで見届けたももクロのライブに、熱く感動・興奮している。
「一緒に舞台をやってるときは、ただかわいい~って感じなんですけど、なんか今日、何万人も相手してステージで歌うれにちゃんの姿を見たら、めっちゃカッコよかったです」といったセリフを口にするが、これは、ももクロと共演した弱めの芸能人が関係者枠でライブを見に行ったときの感想のテンプレートである。
彼らは感動したからこそ、「私たちなんかが関係者として挨拶なんかしに行っていいのか」と不安な思いが湧いてきたことを吐露する。
永野が力強く「いや!!だって俺たち仲間じゃん!!」と後押しする。
そこに、れにちゃんが現れる。
彼らは、ライブに感動したことと、またこうやって会えた歓びを伝え、れにちゃんは屈託なく嬉しそうに応える。
そして、一人が先ほど吐露した、れにちゃんが実は自分たちなど足元にも及ばない遠い存在に感じられてしまうということをポロリと口にする。
れにちゃんの口からも、永野とまったく同じ「なんで?だって、私たち仲間だよ!」という温かい存在肯定の言葉が返ってくる。全員が安堵する。
そのまま和気あいあいと会話していると、一組あたりの関係者挨拶に割り当てられた時間を迎え、マネージャーが「以上です」と剥がしにかかる。
ここからが”オペレーション”になる。
その指示系統たるマネージャーの出現をもって、さっきまで温かくタメ口を聞いていたれにちゃんが「ありがとうございました」と礼儀正しく頭を下げる。
”切断”する。
一同が足取り重くその場を去りつつ、「あれ…?」となっていると、永野が「仲間」であることの再確認のため、来た道を駆け戻り、すでに別の関係者との挨拶に応対しているれにちゃんに向かって「れにちゃーーーーん!!!!!!」と叫ぶ。
それに気づいたれにちゃんは、振り返りもう一度、「ありがとうございました」と深々頭を下げる。
とどめを刺される。
れにちゃんと自分は「仲間」だと思っていたけど、『永野と高城』の共演という場から離れてしまえば、あくまでも自分は「ただの客」でしかなかった、という事実に永野が気づき、舞台が暗転。コントが終わる。
これで『永野と高城。Vol.3』の全コントが締めくくられる。
そのセレクトが、本当に酷い。
2)このお笑いライブは美しかったという話
『Vol.2』に遡った話を書く。
円盤にも収められた『Vol.2』の千秋楽では、最後のカーテンコールでダブルアンコールが発生し、永野はまったく予定外な時間が生まれたために、日ごろなら、自らに禁制を課しているであろう幾分センチメンタルなトークをしてしまう。
その日、永野が劇場に向かいながらウォークマンでニルヴァーナ『アバウト・ア・ガール』が流れてきたとき、いわく言い難い直観が働き、ググってその歌詞の和訳を調べたという。
I'll take advantage while
You hang me out to dry
君といるときだけ俺はうまくやれる
本人曰く、日ごろ「石を投げられながら生きている」永野は、『永野と高城。』のための準備や活動をやっているときだけ、人から「永野さんすごい」と褒められるという。
自分の思いえがくお笑いライブに、ももクロのれにちゃんがいたら、という思いつきから始まり、彼女がそれを快諾して、今日この場を迎えている。
自分にとってれにちゃんは、“君といるときだけ俺はうまくやれる”という『アバウト・ア・ガール』のガールである。
その話を聞いたれにちゃんは、永野は自分なんかと一緒にお笑いをやっていて楽しいだろうかと不安だったことを吐露し、それまで我慢していた涙を滝のように流す。
(先日ラジオ『ももクロくらぶxoxo』であーりんが語っていた話では、この『Vol.2』を終えた後、れにちゃんはしばらく「永野さんと結婚したい」「永野さんと結婚したい」「永野さんと結婚したい」と言っていたらしい)
今回『Vol.3』では、永野の発案によりテーマ曲『ユーアノッアローン』(作曲ヒャダイン)が制作された。
これは若き日のRケリーが手掛けたマイケル・ジャクソン『ユー・ア・ノット・アローン』を元ネタとした(権利関係を指摘されても「そういう動物の名前です」で押し切れるようタイトルを若干いじった)曲であると話された。

このとき、ももクロChanで永野の口からマイケル・ジャクソン『ユー・ア・ノット・アローン』の名前が出たことが、すでに自分にとっては感動的だった。
永野が去年『アバウト・ア・ガール』でそうしたように、好きな90年代の洋楽に、自分が高城れにに抱いている感謝の思いを内在させていることが伺えたからだ。
マイケル・ジャクソン『ユー・ア・ノット・アローン』は、曖昧に書かれた歌詞にさまざまな解釈が存在するが、あえて言えば、愛する恋人に立ち去られた後の男の独白ソングである。
引用:http://musiclyrics.blog.jp/archives/24262435.html
You Are Not Alone -Michael Jackson (1995)
Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're not here with meまた1日が過ぎ
僕は未だ1人でいる
何故こんな事になったのか
君はいない 此処に 僕と共にYou never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold君は決して言わなかった サヨナラを
誰かが言う 僕に 何故だと
君は行かなければならなかったのか
そして残された僕の世界は これほどに寒い
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says毎日 僕は座り込み 問いかける 自分自身に
どうして愛は失われてしまったのか
何かの囁きが 僕の耳元に語りかける
That you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay君は1人じゃない
僕はここにいる 君と共に
たとえ君は遠くにいても
僕はここに留まっている
But you are not alone
I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart
You are not aloneだけど君は1人じゃない
僕はここにいる 君と共に
たとえ僕たちは離れていても
君はいつも 僕の心にいる
君は1人じゃないAlone, alone
Why, alone1人で 1人で
何故 1人でJust the other night
I thought I heard you cry
Asking me to come
And hold you in my armsあの夜
僕は思った 聞いたと 君が泣くのを
頼みながら 僕に 来て欲しいと
そして抱きしめた 君を この腕の中にI can hear your prayers
Your burdens I will bear
But first I need your hand
Then forever can begin僕は聞ける 君の祈りを
君の重荷は 僕が持とう
でも最初に 僕には必要だ 君の手が
そうすれば 永遠に始められるWhisper three words and I'll come runnin'
And I and girl you know that I'll be there
I'll be there囁くんだ 3つの言葉を すると僕は走って来る
僕と君は知っている 僕がそこにいると
僕がそこにいるんだと
いま僕は一人だ、なぜあのとき君は出ていかねばならなかったのか、というウジウジした自問自答から始まる。
しかしサビで「You are not Alone 君は一人じゃない」と宣言する。
いま君は遠く離れていても、”かつて君がいたここ”に、変わらず僕はいるからであると。
彼女は遠く離れてしまったが、いつでも二人が再び出会えるようこの場所から動かずにいる。その可能態を確保していることをもって、「君は一人じゃない」と歌う。
しかし、君が"Three Words 三つの言葉"(アイラブユーの隠喩)を言えば、ぼくは場所的な拘束を解き放たれ、現実態の君の元へ走り出す。
彼女から求められるその言辞によって、自己愛的に固執している”ここ”を離れ、あなたが待つ新しい世界へ動き出すことができる。
これは『永野と高城。Vol.2』の終わりに、れにちゃんがおそるおそる「もしよかったら、来年も、また3をやってほしい」と永野に言い、永野が鳥肌を立て、舞台袖に隠れて「嬉しい!!!!!!!!!!!!!!!!」と叫んだ、あの場面を想起せずにはいられない。
永野はまず、高城れにと自分の間に、同一化できない壁(生eros=肯定を担うアイドルと、死thanatos=批判を担うカルト芸人の自分の間にある壁)を認識する。
それはネガティブな想像の結果でなく、冷静になるほど自覚せざるをえない厳然たる事実である。『れにちゃんが去り際だけ礼儀正しくなるので寂しくなるところ』で、自らへの釘刺しを、共演者・観客一同を巻き込んで行ったように。
しかし、人間にはそれぞれ消化しえない差異があるからこそ「移動」の契機が与えられる。
彼女のもとへ行くことをきっかけとし、彼は新しいレベルへの昇華を試みることができるようになる。
そのようなことを、マイケル・ジャクソン『ユー・ア・ノット・アローン』は主題にしている。
永野はさまざまな場所で、来年もまた『永野と高城。』があることが、それまでの一年間を生きる理由になると語ってきた。それは、自分を必要としてくれた高城れにへの感謝の歓びである。
『永野と高城。Vol.3』の終演を見届けるとき、『ユーアノッアローン』と『れにちゃんが去り際だけ礼儀正しくなるので寂しくなるところ』は、双極を――もっと言ってしまえば永野の双極的な気質を――成しているように思った。
ももクロ高城れにと永野の間にあるついぞ消滅させられない壁に対し、自覚的になってしまう永野と、しかしれにちゃんから求められるなら、いつでもこちらから行く(だから、ユーアノットアローンである)という表明である。
あえて言い換えれば、『Vol.2』のとき、れにちゃんに『Vol.3』をお願いをされ、照れ隠しで「私の機嫌がよければやります」と答えた永野が、一年越しで好きな洋楽越しに「こちらから行きます」というアンサーをしているように思えた。
『Vol.3』の千秋楽でも、れにちゃんは『Vol.4』の開催を永野に求め、従来3Daysだったのを5Daysに拡大してほしいと言ったらしい。
この連鎖が美しい。
以上『永野と高城。Vol.3』は本当に酷いコントばかりで、そして美しかった。
ももいろクローバーZ 舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』感想(第ニ幕) #DYWD
■ヘヴン成長期
ヘヴンを結成した彼女らは、第二幕でももクロ楽曲によるライブを立て続けに行う。
現実そのままの振り付けで再現されるが、それはライブではなく、あくまでもライブの演技である。
高城:歌う部分はあくまで役の中の私たちがやっていることであって、ももクロの私たちではないです。4人で歌ったり踊ったりする曲ももちろんあるんですけど、他の出演者さんたちもたくさん出てくださるので、皆さんにはライブというよりは物語の一つとして見て楽しんでいただけたらいいなと思っています。
このあたりの重層性が、素朴にペンライトを振ったりコールをしてよいのか観客たちが悩む理由になっていて、なんならSNSに上がっているファンたちの感想の3割ぐらいは、ペンライト・コールを巡る鑑賞マナー議論にすらなっているんだけど、まあ、それはいいや。しょうもないから。
ヘヴンは、振られた課題を打ち返すようにライブを重ねるだけで、エスカレーター式にCDデビュー、チャート1位、大型会場でのライブといった輝かしいキャリアアップへと結実していく。
こういう動員の倍々ゲームは、ももクロのキャリアを戯画化した展開だね。
でも、堕天使のミーニャが仕込んだ試練として、3曲ごとの節々でコンスタントにメンバーの脱退に見舞われる。
夢は楽しい。
しかし、<ダンス=夢>は個々人で違う。
だから、脱退・卒業という別れが生じる。
しかし、人間がそれぞれ自由意志を持つというのは本来善いことなはず。
これは肯定されなければならないということを、夢のオーナーであるカナコは重々に理解している。
だからカナコは、辞めていくメンバーに
「それが正解!○○が望んだことなら、それをするのが正解」
「踊ることが楽しい私達は、踊ることが正解!」
と全員を肯定しながら笑顔で送り出す。
そんなライブ→脱退→ライブ→脱退の連続サンドイッチを繰り返すうち、最終的にカナコ、しおり、あやか、れにの4人へとヘヴンは収斂していく。
ヘヴンとして4人で踊っていられる歓びは、事故に遭う直前、前世同等にまで至る。
かつて生まれ変わって不全感に苛まれていた3人が自由、喝采、勇気を手に入れ、そしてカナコはそんな仲間を手に入れたということでもある。
第一幕で示されたオプティミスティックな快楽は、ここまで引き続き延長される。
(もう、口語体は半分諦めるわ。文章に贅肉を足すみたいでけっこうしんどいし)
■魂の疲弊
しかし残酷に、夢は有限であることが示される。
ヘヴンのアイドル活動の集大成になるスーパードームライブの前夜、二人の堕天使が対話する。
坂上は、ここに至るまでカナコの逸脱を許したことについて、カナコにもはや情を抱いているのではないかとミーニャに問いかける。
ミーニャは喝破する。
確かにカナコはかわいげのある存在と言えるかもしれない。
しかし、カナコは転生を拒んだために"魂の成長"の機会を失っている。<時空の鍵>を持たせて泳がせたのは、"魂の成長"のきっかけを与えんとする「偉大なる神への責任感」であると言う。
完全な神が、なぜわざわざ不完全なる人間を世界に配置したのかという問いは、キリスト教神学の古典的なイシューだね。
キリスト教の中では多くの場合、神が人間(に授けられた理性や意志の力)を試していると説明される。
であれば、なぜ魂の転生を司る坂上とミーニャが天使でなく、堕天使であるのか、という疑問も解消される(このへん個人的に気になってた)。
天使とは神の完全性に開かれ、身体性を持たない純粋観念のような存在であるとされる。
いっぽう堕天使とは、"自らのため"に神を求める(最終的には自分が神に置き換わろうとする)という序列の錯誤を犯したために、善悪や真偽といった不完全な対立項的世界へと堕落させられた天使と人間の中間存在である。
ひいては、堕天使とは、神が人間の意志の力を試す体制の一環であるとされる。
(エデンの園に現れた蛇も、こうした構想のもと神に泳がされた存在である)
すると、坂上とミーニャに任されている転生の事務処理業務はあくまでも"方法"であり、それによって達成しようとしている要件は、人間に"魂の成長"をもたらすことである。
二人は、カナコの魂の疲弊に気づく。
転生を拒み、身体という媒体を持たないまま活動するカナコの余力は限界に近づいていて、もうすぐこの夢の世界は終わると。
夢は夢自体のみで存立する純粋観念ではなく、外部資源(魂の身体性)に依存するものだと、ここで気付かされる。
また、夢ないし並行世界論は、歴史が複数化するという問題を孕んでいる。
ありえた世界の束から、恣意的な一つを選んで生きているかのように、すなわち、いまいるこの場所は本質的な一つonenessではないと感じられる空虚かつ再帰的な存在感覚だ。
この問題を、演じ手としてのれにちゃんは正確に理解している。
「(高田れにという役について)何故この子はこんなに不安をかかえているんだろうって…。高田れにちゃんの中にはいろんな自分がいるんじゃないかなって。そのいろんな自分のどれが本当の自分であるべきか、わからない状態?だからこそ不安だし自分自身と葛藤してるのかなって」
引用元:
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』パンフレット P22
■ビューティフル・ドリーマー
並行世界の問題を考えるなら、やっぱりこの作品には触れておきたい。
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の重要な先行的作品として、押井守の出世作でおなじみ『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』がある。
本広克行はもともと押井守オタクとして有名で、インタビューでも『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』は『ビューティフル・ドリーマー』を参照して作ったことを公に語っている。
僕は押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)という作品が大好きなんです。最初は現実だと思っているんだけど、途中でこれはおかしい、こんなにうまくいくのはおかしいとみんなが言い始める。脚本の鈴木聡さんにあの映画を見てもらいました。
引用元:
https://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1008498/091401454/?ST=trnmobile_f
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』は、『ビューティフル・ドリーマー』を見たことがある人間からすると、本当に「あー、ビューティフルドリーマーだ」と思わずにいられない。
(そういう声は、俺以外にも『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の感想を漁るとよく目にする)
『ビューティフル・ドリーマー』の舞台は、友引高校の学園祭前夜。
誰もが翌日の学園祭の準備に慌ただしくしている。
風紀委員会と各クラスが争い、クラス同士も資源確保で対立し、みんなが喧騒に明け暮れながら、同時に命を燃やすような楽しさを憶えている。
そんな中、一人だけ、温泉マーク(という名前の教師)が気づく。
この「学園祭の前日」が、無限に繰り返されているのではないか、ということに。
つまり日がまたがるたび、みんなの記憶がリセットされ、同じ日をループする。
何日も経たないと生じ得ない建物や資材の疲労に気づく。
試しに友引町から抜け出そうと試みても、迷路のように路地が複雑化されているし、それでも町の境目に近づくと、行き止まりにぶちあたる。
友引高校のみんなは、<この時間・この場所>から抜け出せない。
そのことにほかのキャラクターたちも気づくが、ループから抜け出す方法を見つけられずにいる。
この反復世界は、夢邪鬼という妖怪が、ラムの夢――ダーリンや友引高校のみんなと変哲のない幸せな毎日が送りたい――を具体化した世界だと後にわかる。
それが判明したとき、この反復世界を抜け出すべきか、あるいは、幸せなのだからこのままでもよいのではないか、というモダンな問いが生まれる。
人間は、歴史の反復から逃げ出せない。
いま起きている新しい出来事のすべてが、過去すでに起きたことの反復であるように感じられるのは極めて現代人的な感覚だ。
歴史なき反復とは一種の幸福の究極形でもある(すでに完成された幸福のあり方が実現しているなら、人間はただひたすらそれを繰り返せばよい)。
しかし、諸星あたるが導き出すのは、歴史の飽和に人間は耐えられないという結論だった。
彼は、この円環から抜け出すことを選び、その権限をもったラムと夢邪鬼に指示をする。
作中、面堂が重要な指摘をする。
友引町はまったく同じ<ここ・いま>が反復されるのに、コンビニの食料、学校や諸星家の電気ガス水道、新聞配達は尽きることなく供給されている。
街の外とつながっていないと供給されないはずの、ふだん生きるうえでグレーアウトされているインフラだけが何ら変更されていない。
この外部供給の矛盾を面堂が指摘したことが、のちのちこれは夢であるという気付きへとつながっていく。
世界史的に、この事実が露見されるのが80年代以降、湾岸戦争から現在に続くまでの世界だと言えるんじゃないか。
終わりなき日常(できれば使いたくない言葉だけど)も、歴史の終焉(フランシス・フクヤマ)も、観念論の帰結の一種である。
内閉的な自己言及・自己生産によって、際限なく経済(幸福圏)を維持拡張できるという信仰、それの有限性・物質性を晒したのが、アメリカと資源国家との摩擦である湾岸戦争や9.11、あるいは日本の緩慢な日常に対する3.11であった。<夢=非歴史的な反復>の内閉的幸福を支えているのは、身体に養分を与える外部である。
夢の世界は無限ではない。
だから、人間は歴史の環に戻らなければいけない。
ないし、人間は歴史の飽和に耐えられるほど、頑強な存在ではない、というのが諸星あたるが行き着いた『ビューティフル・ドリーマー』の結論だと思う。
■残余する現実
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』にようやく話を戻せば、カナコの魂は、疲労を蓄積する一種の身体性を持っていた。
ミーニャはカナコに、この夢に近く終わりが来ること、それは舞台中央のモノリスに映った月が消え、新月になるまでだと告げる。
ちょうどそのころ、カナコ以外の3人はスーパードームのライブを前後して、話し合う。
ヘヴンの活動はあまりに都合よく進みすぎている、としおりが指摘する。
ライブの直前、存在論的疑問が緊張の音を立てた瞬間、スーパードームの音声が止まり、アンフィシアター全体の客席に照明が灯される。
フィクションである壇上空間に、容赦なく客席の現実が流入し、夢の皮膜が突き破られる。
(という演出がなされる)
我に返った3人から、疑問が噴出する。
しおりの結婚式はどうなったのか?
あやかが次の月曜に控えている演劇部の練習は?
れにが受け持つことになった302号室の田中さんの看護は?
本来生きるべき現実は別の自分たちに任され、いまの自分たちはヘブンが存在する並行世界を生きているのかもしれない。
しかし、転生先である世界がいくつあろうが、そのどれかに振り分けられる魂が一つであれば、魂はユニークな存在なはずだ。
にもかかわらず、自分たち(魂)はここにいる。
並行世界のうちの一人という説明は、整合性に欠けている。
であれば、自分たちの住む世界が変わったわけでなく、カナコの夢の中にいるのではないか?と、れにが正鵠を射る。
いまこうして夢を生きていても、据え置かれた現実世界のコンフリクトは、まったくそのまま保存されている。
また、夢とは歴史を複数化する戯れでしかないことに3人は気づく。<カナコ=ラム>の夢の世界に、彼女らが求める親しい人物たちが引き込まれ、円環的に閉じ込められること。
その空間の非歴史性にさまざまな問題が見いだされることが、『ビューティフル・ドリーマー』と『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の共通点だった。
事の次第を察した3人のもとに、ミーニャと坂上が現れ、れにの明察にお墨付きを与える。
そして私たちと手を組み、カナコに成仏をするよう一緒に説得してくれ。お前たちもあの平凡な現実に戻るべきであると説く。
かつて4人は死に分かたれたため、夢の世界に退避し、非歴史的な幸福圏を作り上げた。
その充足感において、夢は可能である。
しかし、夢を審判するのは夢自身でなく、その外部である。
この展開において、「夢は現実に勝てない」という楔が打ち込まれる。
もはや、夢と現実どちらを是とするかといった二者択一の問題系にとどまるなら、これ以上変わりある答えは出てこない。
とすれば、彼女らが一点突破的に持ちうる解決策とは、「夢と現実」その二項対立のフレーム自体を乗り越えることになる。
これが『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の終盤、クライマックスの問題になってくる。
■「夢×現実」の止揚
カナコはミーニャに、もう少しの夢を続けたいと猶予を嘆願する。
ほかの3人もカナコを信じ、もうしばらく夢を続けたいと願う。
ミーニャは「バカの仲間もバカってことね」と言い、これを拒絶する。
ここで、ももクロ楽曲の中でも光と影の闘争的な色合いを強く持つ『黒い週末』がかかり、堕天使と4人の闘いが始まる。
夢の存続をめぐる決定権は、この舞台の中心を占める者たちに託されると言わんばかりに、ミーニャと坂上が従える堕天使の集団が『黒い週末』を歌い、4人を端へ追いやる。
牽制をそれとして理解する様子もない4人は、わきの階段で堕天使たちの歌と踊り(マジで上手い)を楽しそうに眺める。
あーりんは途中どう見てもペンライトを振る動きをしている。
しかし、いたずら心から4人は舞台に返り、あーりんとミーニャが、カナコとミーニャが互いのパートを奪い合い、『黒い週末』を、ミュージカルの醍醐味であるグループ闘争の歌曲へと仕立て上げていく。
これまで和解の契機となる音楽はつねに『Do You Want to Dance?』だったが、例外的に『黒い週末』がその機能を果たす。
ラスサビ(ラスト・サビの略)で、"その曲のオーナーであるももクロ"と"歌唱とダンスのプロであるミュージカル俳優"たちがダンスを共にし、互いの強度を一体化させる恍惚には脳を溶かされる。
見終えた後、識字能力がガクンと下がる。
歌が終わると堕天使たちは疲れ果て、舞台の中心を4人に明け渡す。<時空の鍵>をもうしばらく貸してほしいと言うカナコに対し、ミーニャは渋い顔をしながらも、一度試練を与えた以上、結末の付け方まで彼女らに一任することを選ぶ。
4人は<時空の鍵>をかざし、前世でいつもダンスの練習をしていた体育館裏に移動した。
あれほど夢見たダンスコンクールよりも、こっちのほうがずっと宝物のような場所であるとカナコは言う。
ダンスの当初の認識は、欲望としての夢だった。
キラキラとして、ワクワクするもので、具体的には、自由、喝采、勇気、仲間だった。
しかし4人で夢の時間を過ごしてきた中で得られた認識は、結婚、演劇、病院といった現実世界での抵抗の身振り手振りもまたダンスであるということだった。
現世もまた夢同様にかけがえないことを知る。
カナコは、3人が現実へ帰った後に行なう"ダンス"を「楽しみ」に思うと言い、「ダンスじゃなくても、ダンスなんだね」と受け入れる。
ダンスを夢というトポスに限定させる必然性や権能はない。
夢が終われば、夢の記憶は消えると堕天使たちにかねがね説明されている。
また街中で会ったとしても、私たちは互いを忘れているのかな?とあやかが尋ねる。
忘れないよ、忘れるわけないじゃん、だから、さよならは言わない!とカナコはおちゃらながら答える。
この夢を終えることを決めた彼女らは、別れることを選んだのではない。
"忘れないこと"への賭けをした。
体育館裏の吹きすさぶ風の音の中、アカペラで『Do You Want to Dance?』を口ずさみ、4人最後のダンスを行う。
モノリスに映る月の下、ダンスを行うのは、「Well do you wanna dance under the moonlight?」という原曲の歌詞を想い起こす。
しかし、その月は『Do You Want to Dance?』を踊り終えると同時に消えていく。
舞台は暗転し、彼女らは地下に消える。
坂上とミーニャが現れ『世界の秘密』を歌い、生まれ変わりによって分かたれる彼女らの因果を憂う。
再び4人が現れ、この舞台に当て書きされた新曲『天使のでたらめ』が歌われる。
(これはもう月が消え、カナコの魂が限界を迎えているはずの状態での延長的な戯れである)
Aという夢と、このBという未来があって、神さまがいるならAとBをイコールにしてほしい。
生まれ変わっても忘れない。
嫌になるほど見つめてよ。
という歌詞が歌われる。
「夢と現実」の二項対立を超克し、一つの世界観に収斂されることを祈る曲だ。
この曲は一種の対話劇だったと思う。
一つ目は、堕天使たちが『世界の秘密』で「転生で忘れる」ことが歌うのに対し、『天使のでたらめ』は決して忘れないことを宣言する。
二つ目は、カナコが顔貌や癖の一つひとつを忘れないと言い、「だから来世でもよろしくね」と歌うのに対し、3人は「嫌になるぐらい見つめてね。忘れないでね」と再会の約束に応じる。
カナコは「魂の成長」の契機を与えられた。
それは天界が描くシナリオのとおり、最終的には生まれ変わりと忘却に着地するよう約束された戯れのはずだった。
『天国のでたらめ』は曲名のとおり、そんな天界の規定に抵抗する宣誓歌である。
ないし、この舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』とは、何者でもない愚かな人間が、天界にとって計算不可能なモーメント、すなわち奇跡を生み出す過程の物語だった。
■先行物としての『Re:Story』
少し舞台のストーリーから外れる。
『天国のでたらめ』が「Aという夢とこのBという未来」を「イコール」にするよう求めるという構成に対し、たちまち想起させられるのは、つい8月に配信リリースされたばかりのももクロの楽曲『Re:Story』だった。
これは『Re:Story』が発表された直後、ジャケットイラストにウケて呟いた内容なんだけど、青々しい夏の静けさの中で、少年たちと宇宙人というまったく異なる歴史の並走が描かれている。
楽曲配信よりも若干遅れて発表された『Re:Story』のMVでは、この少年たちと、UFOから墜落した宇宙人の少女が薄暗い森のなかで出会う。
宇宙人の少女は、紫色の服を着たレニスという少年に霊力を施し、ファンキーなダンスを踊らせる。
少年たちはいたく感動し、宇宙人の少女のもとに駆け寄る。
ここでもダンスは、異なる文化(星)の者同士が無根拠に一体化しうる契機として扱われている。
『Re:Story』とは、再帰的な歴史のことを指すだろう。
ももクロのファンにとって、どうしても視線を反らし難い問題を言えば、2018年は緑担当の有安杏果が卒業した年であり、ファンもメンバーも、その精神的格闘に明け暮れた印象が強い。
4人になった新生ももクロは、スクラップアンドビルドを余儀なくされた。
いかなる困難にさらされても「逆境こそがチャンスだぜ」と捉えるのが、ももクロのクラシックナンバー『ピンキージョーンズ』の教えであり、有安卒業の2018年1月以降、いくどとなく、メンバーやファンの口からこの言葉が唱えられてきた。
このとき歴史は、「本来ありえた理念的な正史(5人のももクロ)」と「軌道修正する現実態の歴史(4人のももクロ)」に分岐する。
歴史が複数化する。
人はその比較に絶えず足をつかまれる。
ファンは、ももクロのライブやフォーク村(というももクロが歌唱力・表現力の成長を月次報告するような楽しい番組があるんだよ)など、さまざまな場で「ここに杏果がいたら」と想像させられる。
『Re:Story』とは、逆境へ立ち向かうときに必然的に伴う歴史の分裂であり、精神に課される肉離れの鋭痛である。
しかしこの歌の最後は、リ・ストーリー(再・物語)からザ・ストーリー(この物語)という単数形への言い換えで結ばれる。
ももクロの複数化しかけた歴史(あえて選ぶほかになかった歴史)を、再び単一の歴史(これしかありえない歴史)へと収斂させようという宣言に映る。
『ピンキージョーンズ』のイズムにパッチを当てる、新生ももクロに捧げられた曲のように8月当時の俺は感受した。
夢(ありえた並行世界)と現実(これ以外ありえない歴史)を揚棄・収斂させるという問題は、『Re:Story』から『天国のでたらめ』において通貫している。
『Re:Story』がつい2ヶ月前に発表された楽曲と考えれば、舞台制作と音楽制作が互いを参照し合った可能性は低いだろうけど、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』と『Re:Story』はどちらも、ももクロの今日的な痛みを優しく慰撫してくれる。
■夢
『天国のでたらめ』の途中、一人だけ先に消えたカナコは、その曲が終わると舞台脇から白い衣装をまとった天使になって現れる。
ついにカナコが昇天するときが来た。
カナコは「ここはどこだっけ」「名前なんだっけ」と、前世や夢の出来事、名前、時系列を順に忘れていく様を歌う。
他の3人は、自らの手足、衣装、立っているその場を見て戸惑う様子を見せ始める。
カナコの成仏に伴い、彼女らもこの夢の記憶が薄らぎ始めているのだ。
人々が毎朝経験しているとおり、夢はどれほど強烈な印象を残す内容であっても、エピソード記憶としてはたちまち揮発する。
しかし、夢は厳密には忘れない。
フロイトが言うように、人間が防衛機制として記憶を絶えず忘却していったとしても、反復強迫は残余する。
忘却された記憶は、あくまでも「抑圧されたもの」でしかない。
夢の世界を、エピソード記憶としては忘れたとしても、そもそも夢によって表現されるのは、現実の出来事が<暗号化=象徴化>された「形式」だった。
出来事でなく形式であるがゆえに、記憶すること(現実に引き継ぐこと)ができない。
しかし出来事の外郭である形式において、夢はいつまでも反復しうるものとして無意識の中に保存されている。
形式が残余するから、それに即した出来事に見舞われたとき、人は懐かしさ、いわゆるデジャヴを憶える。
逆説だが、忘れるとは一種の記憶術であり、夢はその整理である。
記憶を出来事(図)から形式(地)へと変換・圧縮し、半永久的な耐久処理をかける。
エラスムスも「痴愚」の構成物の一つに、「忘却(レテ)」を挙げていた。
それは硬直した老人を若返らせる、いわば転生の術であると。
考えてみれば、カナコの働きかけによって再会した4人は、だからといって交通事故に遭う前の、富士が丘高校のころの記憶が甦ったわけではない。
ダンスを通じて強烈に感じられた「懐かしさ」が、この4人は本源的に出会うべき4人であるという言い知れぬ確信を彼女らにもたらしただけだった。
ないし、4人が再帰的に夢を実現するうえでは、その確信さえあればよかった。
記憶は死や覚醒をもって揮発するが、この4人がまた集うという形式は確保されている。
4人が賭けたのは、そうした意味での「忘れない」ことへの信頼、強度である。
それはあの再会のとき、ダンスによってすでに触知している事実だった。
ワイヤーに吊られて昇天していくカナコを、もうカナコと分からないかもしれない3人が静かに見上げている。
そこに坂下とミーニャ、大勢のアンサンブルの俳優たちが集まり、ももクロの楽曲『HAPPY Re:BIRTHDAY』を歌い、カナコの転生を祝福する。
(ここはまさに天界の楽団という趣で、『黒い週末』に続いてミュージカルの恍惚を極めてくれる)
歌い終えると、しんしんと雪が降り始める。
ももクロの4thアルバム『白金の夜明け』のイントロ曲『個のA、始まりのZ -prologue-』が流れ出す。
これは『HAPPY Re:BIRTHDAY』のメロディをオルゴールで再現し、3rdアルバムのラストから4thアルバムの始まりへと接続する郷愁的な調子の楽曲である。
舞台は、夢から現実(来世)に切り替わる。
大勢のアンサンブルが行き交う様子は、かつて4人が事故を起こした渋谷区の交差点のようにも見える。
現実へと返ってきたしおり、あやか、れにの3人が雪が降る街に現れる。
互いを知らない者同士として、スマホを眺めながらバラバラに歩いてくる。
少し遅れて、来世へ転生したカナコ(であった女性)が現れる。
3人とカナコがすれ違う。
カナコは歩みを止め、懐かしい何かを感じる。
カナコは立ち止まるが、決して、しおり、あやか、れにという3人の名前やエピソードを覚えている(あるいは思い出す)わけではない。
形式として、この3人はかけがえのない存在であるという指向性intentionのみが強烈に喚起されていることが、ざわついたカナコの表情から察せられる。
カナコは3人のもとへ走り出し、「すみません」と声をかける。
逆光に向かって駆け寄るその姿で、舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』は終わる。
このとき『個のA、始まりのZ』はインストゥルメンタルとして流れるが、ファンは否応なく、この曲に本来あてられた歌詞を頭の中で再生させられる。
それは夢からの目覚めであり、視界がぼやけた朝焼けの世界の歌詞である。
眠って 起きたら また始めよう
夢の中で まだZzz
あんまり のんびりしていられない
早くいきたい でもZzz
たくさん計画があるんだ
待ちきれないよ
あずかったままの愛を かえそう
カナコが3人を追いかけ、声をかけるとき、この曲に本来流れる歌詞はこうである。
懐かしい場所に立とう きみのもとへ
出逢おう あたらしい自分を みせよう
この言葉とカナコの駆け寄る後ろ姿が、心の中でオーバーラップされるとき、何度鑑賞しても涙が溢れてくる。
夢を終え、また凡庸な現実に帰った彼女らは、記憶(出来事、名前、時間、場所)の一つ一つはリセットされた。
なのに、同じはずの現実がその調子を変える。
何故なら、夢はいつまでも形式において残余するからだ。
それが夢の強さであり、夢は決して無力ではない。
これこそが世界を駆動する源泉である。
「この4人」は現実においても、いつまでも続く。
その祝福に満ちて、舞台は締めくくられる。
〜〜〜
と、だいたい以上が、舞浜アンフィシアターに5日連続通いながら、俺が感じたこと・思ったことをとっちらかした無惨な結果なんだけれども。
メンバーがさまざまなインタビューで語るとおり、この舞台は、観た人に、本当に大事なことの気づきを与えようとする生の讃歌だと思う。
あと、「生と死」「現実と夢」という二枚貝的なモチーフを絶えず往還する『AMARANTHUS』『白金の夜明け』が土台となっていることは、いかなるライトなファンでも容易に気づける。
だとすれば、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』は、『AMARANTHUS』『白金の夜明け』のフレームから、『Re:Story』『天国のでたらめ』といった現在形のももクロへと接続される舞台作品であると感じられたな。
それら二曲が新生ももクロに捧げられた祈りの曲であるように、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』という舞台も、ももクロの4人が4人でいることへのアファーマティブな祝福に満ちている。
思えば、毎日劇場を出るたび、急いでiPhoneを開いて感想をEvernoteに書きなぐったり、家に帰ってからさらにExcelで時系列を図表化したりするのが、楽しくて楽しくて仕方なかった。
自らの作品理解に追加・修正がかかる限り、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の肌理に触れ続けられているように感じられた。
その快楽は7回の鑑賞の中で、いまだ途切れていない。
俺にはまだ4回分のチケットがあるし、明日2018/10/5(金)の夜公演から『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の快楽が再開される。
そういう自分にとっての"後半戦"の前に、あーりんが言う「思ったことや感じたこと」に区切りをつけられたのは良かったかもしれない。
あーりん、そんなきっかけを与えてくれてありがとう。
また明日、あなたを、ももいろクローバーZを、舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』を見に行きます。
〜〜〜〜〜〜
参考図書:
エラスムス『痴愚神礼讃』
柄谷行人『歴史と反復』
野田努『ブラック・マシン・ミュージック』
岡崎乾二郎(編著)『芸術の設計』
八木雄二『天使はなぜ堕落するのか』
ももいろクローバーZ 舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』感想(第一幕) #DYWD
■プロローグ
で、順に展開を舐めていくと、ファンとしては、まず先に語った交通事故に見舞われるイントロダクションで泣いてしまう。
落差がすごい。
翌日のダンスコンクール決勝を控え、みんな軽い躁状態になっている。
カナコは、勉強ができない。
いわゆる"どや顔"で、『Do you want to dance?』の冒頭部分「Do you want to dance and hold my hand? Tell me baby I'm your lover man.」という歌詞を、荒井注レベルのカタカナ英語で話すんだけど、
「ドウーユーワナダァン? アン…アッポー オン マイハンズ」と、ピコ太郎にあやかる。
くだらなさに4人とも笑う。
カナコはヘッドホンをつけ、ここ(交差点)で練習しようと言い、4人は踊り出す。
ウキウキとしたビートで楽天的な雰囲気に包まれたとき、ふいに暗転する。
ドガン ガシャン
とトラックの前面が派手にへしゃげるような衝突音が真っ暗な空間に響く。
少し間を置いたのち、4人の死亡を告げるニュース音声が流れ始める。
併せて、荘厳なメロディの、ももクロ3rdアルバム『AMARANTHUS』のイントロダクション『embryo -prologue』が流れる。
真っ暗な舞台の正面には、本広克行が『2010年宇宙の旅』から引用したと言っている巨大なモノリスが屹立していて、そこにタイトルロールが映し出される。

(本広克行は『幕が上がる』で寺山修司『田園に死す』を引用するのしかり、引用対象のセレクトと仕方が映画学科の大学生っぽいんだよな…)
こんなの、ももクロのファンとしては、眼球を取り出されて果汁搾りに押し当てられるように、涙が強制的に絞り出される。
「ももクロに、もしこんなことが起きて、こんなニュース音声を耳にしたときには、自分はもう生きていられない」と思わずにはいられないから。
(ただ、これぐらいあざとい冒頭の演出は、決して嫌いじゃない)
タイトルロールが流れ終わると、舞台中央の空洞から床がせり上がり、魂となった4人が『WE ARE BORN』をアンサンブルたちと一緒に歌い出す。
これも3rdアルバム『AMARANTHUS』の収録曲ないしリード曲なんだけど、
イントロダクション『embryo』からシームレスに『WE ARE BORN』へつなげられるアルバムの仕組みが、舞台へとそのまま移植されている。
胎内から不完全な世界へ産み落とされる不安と、しかし胎外から差してくる光に向かい進んでいこうという勇気が歌われる曲だ。
つまりは、死んだ4人が生まれ変わるモーメントがここで表現される。
だけど、先に言ったとおりカナコだけが死を自覚できず、天界を浮遊している。
『WE ARE BORN』のオチサビ前に、カナコ以外の3人は舞台から地下へ消えていくんだけど、
カナコだけ曲が終わると、「れにー、しおりー、あやかー」と3人を探し始める。
そこに魂の転生を司る堕天使ミーニャと、その部下の坂上が現れる。
(ミーニャがシルヴィア・グラブ、坂上が妃海風という俳優さんで、どちらも歌劇のマジのプロ。一挙一動すばらしいので、本当に出演してくれてありがとうという気持ちしかない)
堕天使の二人は、あの日4人とも交通事故で死んだこと、そしてまだ生まれ変わっていないのは、死に気づかずにいるおバカのカナコだけであると説明する。
『世界の秘密』という曲を歌い、天界が定める転生の仕組みをカナコに教える。
「生まれ変わりはある。それは過去から未来でなく、壁の向こう側の並行世界」であると。
魂が転生する先は、死んだ直後の同一世界とは限らず、時代はかえってむかしに遡るかもしれないし、場所や、どの並行世界なのかも変わりうる。
そうした転生先は、ミーニャによってガチャポンでランダムに決められると。
確かに並行世界が前提とした世界であることを、ファンは随所で気づかされるんだよね。
交通事故のニュース音声が流れるとき、ダンス部の4人は富士が丘高校の学生であると言われるけど、これは『幕が上がる』の演劇部がある学校名なんだ。
後に、あーりんがまさに『幕が上がる』の演劇部へ転生していることが分かるんだけど、そこでは、前年の高校演劇のブロック大会で敗退したことになっている。
『幕が上がる』では、高橋さおりという部長の奇跡的な台本・演出でブロック大会はもとより全国大会まで勝ち進むことになっているので、『幕が上がる』とは設定がずいぶん違っている。
そもそも転生したあーりんの役名も『幕が上がる』の"加藤明美"でなく、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』では"渡辺あやか"になっている。
渡辺あやかが転生した先の富士が丘高校には、前世で所属していたダンス部は存在しないことになっている。
別に時代が大きく異なっている様子もない(どちらの時代でも、YouTubeの存在が自明に語られている)
こんな具合に、ファンなら瞬時で分かる世界のねじれが節々にある。なるほど、並行世界なんだなと。
やや拙速にあーりんの話へ逸れちゃったけど、カナコは、さあ、転生するわよとガチャポンを回そうとする堕天使たちの説明を受け入れられず、さまざまな並行世界を自由に行き来できるという球体<時空の鍵>を奪い、その場から逃げ出す。
慌てて堕天使たちが追いかけようとすると、ミーニャがまた悪そうな笑顔で、急ぐ必要はない。カナコを泳がせてみようと言う。
退屈しのぎとして、カナコを試してみようと言う。
(ただし、カナコを泳がせる動機付けは、物語の後半で重要な訂正が入るんだけどね)
■再会
カナコが<時空の鍵>を使い、しおり、あやか、れにの元へ行くと、3人は生まれ変わった先でそれぞれ冴えない日々というか、不全感を抱えて生きているんだよね。
しおりは、結婚を来月に控え、ウエディングサロンでマリッジブルーになりかけている。
親がお膳立てした縁組を受け入れる「いい子」な自分について、その規範を内面化している自分と、空虚に感じる自分とで分裂し始めている。
あやかは、富士が丘高校演劇部の部長を『幕が上がる』の主人公高橋さおりから引き継いでいるんだけど、さおりのような求心力を持てずにいる。
部員たちが演劇にシリアスになってくれないことに苛立っているし、そんな状況に押し流されそうになっている自分の弱さにも懊悩している。
れには、看護師としてオーバーワークの日々に明け暮れている。
仕事にいい加減な同僚たちから、つい率先して面倒事を巻き取ってしまう。
昼ごはん(なぜかフリスビーぐらいの大きさの肉まんを持っている)を食べる時間も取れずにいる(デカすぎるからでは?)
そんな献身的姿勢は、彼女の自信のなさ、弱さに由来している。
こうした3人との再会が、各々のソロパートの歌唱とともに演じられていく。
ももクロのライブをいつも見ている人間としては、玉さん(玉井詩織)、あーりん(佐々木彩夏)、れにちゃん(高城れに)の3人ともが、本当に丁寧に歌ってくれているのが分かる。
バイオリンの音のように、実にきれいに声が伸びていく。
で、3人それぞれのもとへ突如現れたカナコが「久しぶり〜〜〜〜」「また一緒に踊ろうよ〜〜〜〜〜」と駆け寄ると、彼女らは当然、何だこいつは?とめちゃくちゃ怪しがる。
もはや彼女らに前世の記憶、カナコの記憶はないから。
なのにカナコが『Do You Want to Dance?』を口ずさみながら踊ると、3人とも、体が勝手に踊りだす。
踊りながら、自らの手足を眺めて「????」と戸惑う(あーりんだけニヤニヤして、何これウケんだけど、ってなってるのが良い)。
また、なぜかカナコが口ずさむ『Do You Want to Dance?』を聴くと、胸の奥がポカポカしてくると言う。
3人はその言い知れぬ心地よさに、直感的に、いま苛まれている不全感から抜け出す光のようなものを感じ取り、つらい現実(ウエディングサロン、演劇部、病院)を置き去りにして、カナコを追いかける。
個々人パートの最後にあたるれにちゃんが走り出したところで、ももクロの楽曲『LOST CHILD』が歌われる。
直訳して「迷子」。
後々暗示されるけど、このタイミングをもって、3人はカナコが作り出した夢の世界に入り込む。
彼女らが<いつ・どこ>性を失い、(存在感覚的な)迷子になることが歌われているんだ。
この場所はどこなのか問い詰めても、カナコはふんわり「それは私にも分からない」「ロビンフッドがいた森かもしれないし、昭和の時代の近所の公園かもしれない」と答える。
しおりが「私達をこんなところに呼び出してどうするつもり?」と詰め寄る。
カナコは「私が呼んだんじゃないよ。みんなが勝手についてきたんじゃん」と切り返す。続けて「4人でゆっくり話す場所がほしかったの。だから、ちょっとカフェに行くみたいに、これ(時空の鍵)を、ヒュッ、と」と語る。
(一応言っておくけど、俺、会場でコッソリ録音して文字起こしとか、そういう違反行為はやってないからな)
つまりカナコは、3人を誘い、この<いつ・どこ>性を持たないトポスを準備するところまでを行った。
3人はカナコを追いかけ、その世界に入り込んだ。
この双方の積極性がペアリングしなければ、4人で再び集まることはできなかった(カナコ一人の強制力で結集されたわけではない)という事実が示されている。
彼女らは、体に染み付いた『Do You Want to Dance?』をあらためて4人一緒に踊る。
すると潜在していた快楽(=振り付け)が噴き出すように、かつての戸惑いが取り払われた調子で、4人の手足が美しい動きを描き始める。
ダンスを共有することを通じて、かつて死で分かたれた4人が再び合一を果たす。
(いまさらだけど、情報をどんどん羅列的に書いていく局面だと、口語体が全然成立してくんないな)
■ダンス
ここらへんでいったん、この舞台作品において、ダンスとはどういう位置づけなのか補助線を引いておきたい。
そもそも舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』とは、「みんなとダンスがしたい!」という情動を扱う話。
では「ダンス」とは何なのか?が常に問題化される構造になっている。
まず、この舞台で『Do You Want to Dance?』は、共同性を取り戻す契機として繰り返し用いられる。
カナコが3人それぞれと出会い、潜在的な記憶を引き出すためのトリガーとして。
また、4人全員集ったときは、面識を持たずアトランダムでしかなった4人から、共同性を持った4人へ再帰する契機として用いられる。
この楽曲の魔力はすごい。
『Do You Want to Dance?』が踊られれば、言葉による説得がされたわけでもないのに、根拠もなく、一緒に踊った人たちは共同体になる。
こうしたダンスの機能は、さまざまな分野で指摘されていることだと思う。
羅列的な知識で恐縮だけど、たとえば、野田勉『ブラック・マシン・ミュージック』。
ディスコ、ハウス、テクノといった20世紀後半の電子音楽が、シカゴやデトロイトのような荒廃した都市の黒人たちによって形成されてきた歴史のダイナミズムを丹念に追う、
まあ黒人音楽の研究書としては、上梓以降、一貫して最重要であり続けている本だけども。
この本が繰り返し訴えるのは、ダンスとは、歴史の異なる者たち(住む街、所属するトライブ、人種、貧富の差)を脱意味/脱歴史化し、同じリズム反復のるつぼの中に溶かし込む機能を持っているものだということだ。
たとえば、チビクロサンボの虎たちが木の下の回転のうちに、一つの溶けたバターになっていくように。
音楽の享受方法にダンスが採用されたことで、70年代以降の電子音楽は、異ジャンルの融合時に本来ありうる調整コストが極めてやすやすとクリアされ、加速度的な発展と拡張を遂げたことを指摘している。
ほかにも、パンコパンダや未来少年コナンを始めとした宮崎駿のアニメにおいて、互いの動きを模し合った者同士は漏れなく"仲間"になることを、ササキバラ・ゴウが『教養としての〈まんが・アニメ〉』で分析してたな。
何よりわかりやすいのは、マイケル・ジャクソンの『Beat it』および、それを参照して撮られたももクロ『DECORATION』のMVだ。
元々対立したチーム同士のチンピラたちが、何も対話はしていないのに最後に大団円のダンスをするだけで合一していく。
とりとめないけど、再三確かめておくべきは、ダンスとは<根拠なき合一>であるということだ。
■起点としての「バカ」
もう一つ、この物語の重要なファクターとして、すべての始源にカナコの「バカ」さがあるということに触れておきたい。
それは、カナコが自分や他3人はもう死んでいることに気づかなかったバカさであり、
また堕天使たちが歌う生まれ変わりのルールを少しも内面化しようとしないバカさが、物語に奇跡を起こすすべての契機となっている。
このフレームは台本の鈴木聡によるものだって、本広克行も語っている。
本広克行 ミュージカルだし、夢の話だから、歌うことも踊ることも何でもやれるんだけど、できあがった脚本を読んで、素晴らしいと思ったのは、それらを結びつけるのが「バカの力」だということ。鈴木さんのすごいアイデアですよ。死んだことも生まれ変わることもイヤだといって、4人が一緒にいる夢を見続けるカナコの物語。僕はやっぱり何かを作り出すのはバカだと思うんです。
引用元:
https://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1008498/091401454/?P=3
なんなら、この舞台の時間の8割ぐらい、カナコは「あは〜」な笑顔というか、彼女の頭上に小学生がよく描く花弁が放射状の花が一輪咲いているのが、ありありと目に浮かぶ。
ここらへんで急にお硬い言葉を使い始めるけど、そんな姿を見て否応なく想い起こされたのは、エラスムスの『痴愚神礼讃』だな。
2〜3年前に読んだとき、俺には、この中世に書かれた本が"ももクロ礼賛"、それも特に"百田夏菜子礼賛"にしか読めなかった。
『痴愚神礼讃』っていうのは、中世の人文主義者エラスムスがカトリック教会や、それを理論的に支えるスコラ神学を批判した諷刺書として知られている。
痴愚女神moriaが、自画自賛の弁舌を奮いながら、対称的に硬直しきったカトリック教会やそれに関連する人々をこき下ろしまくる。
この本がルターに共感を与え、宗教改革の起爆剤になったことは有名だね。
むろん、ここで検討すべきは宗教史的・文学史的意義のどっちでもない。
痴愚を礼賛する理路を一瞥する必要がある。
痴愚女神は、自らの良いところ、痴愚の美徳をいくつも挙げる。
うぬぼれ(ピラウティア)、追従(コラキア)、忘却(レテ)、怠惰(ミソポニア)、快楽(ヘドネ)、無思慮(アノイア)、逸楽(トリュペ)、お祭り騒ぎ(コモス)、熟睡(ネグレトス・ヒュプノス)…
と、ふつうは一蹴されるべきこうした痴愚の要素を丹念に、これがあるから人は生殖ができる、これがあれば人は若返る、とその効能を訴えていく。
ここで大事なのは、人間の感覚的回路はきわめて分裂的で複数化していることを、ひたすら痴愚女神が説いていくところだ。
主体を統御的・単一的にまとめあげる理知性よりも、情念や快楽のほうが感覚回路のレパートリーが多種多様に開かれていると。
エラスムスいわく、理知性が1だとすれば、情念の種類は24個あるとすら言っている(内訳はあんまり説明されないけど)。
もちろん、エラスムスは素朴に反知性主義を唱えているわけではない。
合理性批判とは、漏らさず合理性のアップデートをはかることを本義としている。
知性や敬虔といった狭い回路に閉じるよりも、歓びを軸とすることで、より人間は広く世界に開かれる。
大局的に見れば、そのほうが知的・合理的ですらあると。
これを現代の用語で説明すれば、痴愚神礼讃は、リダンダンシーの古典的理論書であると言えるだろうな。
リダンダンシーとは冗長性のこと。
おそらくIT開発とか、なんかの業務プロセスを設計している人とか、ビジネスの畑でこそよく使われる言葉じゃないか。
たとえば機構Aと機構Bはそれぞれ維持コストがかかる別個のシステムなのに、もし一部の機能が重複しているとしたら、それは冗長であると言える。
ふつう合理的に考えれば、システム全体の中で、一機能は一機構にのみ与えることが最適とされる。
でも20〜21世紀のエンジニアリングが気づいたのは、一見合理的に捉えがたい冗長な構造のほうが、往々にしてサステナビリティ(持続可能性)に優れているということだった。
機能を複数化させることで、一つの機構が潰れたときに即時補完ができる。
一個のアンテナが潰れても、別のアンテナの角度調整をするだけで、完全機能停止という最悪の事態を防げる。
また、同じアウトプットであっても、異なる回路・アプローチから得られた結果を相互参照することで、より精度の高い反証的判断が得られる。
同じように人間の身体感覚も極めて冗長に組織されているというのが、アフォーダンスをはじめとする20世紀の認知科学の気づきだったと思う。
人間の知覚・動作を観察すると、デカルト的な心身二元論(脳=知性が身体を統御する)では説明できない様態が数多く発見される。
手足は手足自身が考え、皮膚は皮膚として記憶を持ち、内臓や細胞ですら脳の統御に抵抗し続けている。
こんな具合に、人間身体とは分裂的な一種の闘争の場であるというのが、20世紀以降の生態学の基本的な理解だと思う。
考えてみれば、ダンスというジャンルそのものが、人間は認識の回路がさまざまに分裂していることに対し、極めて自覚的なジャンルだと言えるんじゃないか。
他者に披露したい(視覚的に把握された)動きと、それを生み出すダンサー自身の身体イメージは往々にして一致しない。
つまり、ダンスをビデオテープによって客観的に記録し、それを振り付け情報として人を与えても、そんな視覚的理解でただちに人間は踊れるようにはならない。
必ず、併せて身体感覚への翻訳が求められる。
逆に、一度身体が憶えたダンスは、目をつむりながらでも再現することができる。
カナコたちが死によって、生前の出来事や友人知人の名前といった海馬的な記憶を失っても、身体性を持った魂が直接感覚を保管していた。
そんな前世の感覚を引き出す鍵がダンスであるということが、この舞台作品では執拗に描かれている。
ひいては、おバカのカナコこそ、他の3人よりもリダンダンシーの強度が突出していた。だからこそ、4人を再びつなぎ合わせる契機になりえたということだと思う。
これは現実のももクロにおいても日々認識されていることだ。
本広克行は『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』を巡るインタビューで、あーりんが「百田夏菜子がいなかったらももクロなんかできないから」と話していたことを語っている。
ともあれ押さえておきたいのは、痴愚やダンスといった劇中用いられるモチーフはすべてが論理的に結びつき、ストーリーで起きる奇跡を下支えしているということだ。
作劇を務めた鈴木聡は、やれ並行世界だとか、やれおバカといったフレームをなんでもありのマジックワードのようによく自嘲しているけど、全然胸を張ってよいと思う。
■ヘヴン結成
話を『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』のあらすじに戻すと、再び結集した4人は、<時空の鍵>をかざすと誤ってアイドルのオーディションに飛び込んでしまう。
なし崩しに課題曲を踊り、面接で「あなたたちにとってのダンスとは何か、一つの言葉で説明しなさい」と振られたとき、彼女らは自分にとってのダンスの定義を明言していく。
しおりは「自由」
あやかは「大喝采」
れには「勇気」
カナコは「仲間」
各々が自らに欠けていると感じ、欲望していたものを宣言するというのはオズの魔法使いのようだけど、すなわちダンスとは、人間が欲望するところの「夢」である。
オーディションに受かった他メンバーを含め、9人で『Do You Want to Dance?』を踊る。
Bobby Freemanの原曲どおりの曲構成で、大人数によるフォーメーションの広がりはミュージカルの醍醐味をはつらつと見せてくれる。
曲が終わって全員が決めポーズをした瞬間、アイドルグループ「ヘヴン」が結成される。
ここでも楽曲『Do You Want to Dance?』は、異なる歴史を持つ者同士を一つの束に収斂させるものとして呼び出される。
この舞台には、夢はいかにして可能か?という問いがあった。
であれば、<ダンス=夢>という構成のもと、その多幸性・冗長性を描くことで夢は可能であるとアファーマティブに示される。
この楽天性へ回帰するところでもって、舞台前半である第一幕が終わる。
ももいろクローバーZ 舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』感想(導入) #DYWD
いま、ももクロが舞台というか、ミュージカルが絶賛やっててさ。
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』っていうタイトルのを。
舞浜アンフィシアターっていう本来シルク・ドゥ・ソレイユ用に作られた劇場で。
9月下旬〜10月上旬にかけて、合計19公演やるわけなんだけど、そのうち9月分の7公演を見てきたんだわ。
俺が。好きだから。ももクロが。
あと今週末も、もう何回か見て、合計11回見ることになるのか。
ヤバいな。幸せだな。とんかつ食べながらAV見るよりずっと楽しいわ。
いやさ、おもしろいんだよ。
何度も涙するし、笑わされる。
俺はもはや、ももクロを客観的に評価する視力を完全に失ったファンだけど、それでも頭の中で丹念に形式を追う限り、おそらくコンテンポラリーな枠組みから見ても、非常に美しく作られているんじゃないかと思う。
で、この舞台作品なんだけど、あーりんっていうももクロのピンク担当の子、まあアイドル用語でいう俺の"推し”の子がね(こういうことを言うの恥ずかしいけど)
パンフやいろんなインタビューの場で、この作品を観終わったらぜひ、友だちや家族と感想を語り合ってほしいって呼びかけてるんだよね。
佐々木彩夏
私は映画を観たり、演劇を観たり、美術館に行った後、思ったことや感じたことを話すのが大好き。だから、この舞台を観た後、お友達や家族で、わいわい話して盛り上がってほしいな。転生とか、パラレルワールドとか?正解がないことについて、それぞれの想いをみんなで話してほしい。その時間が楽しいなって思うので。
そしてみんなの話が盛り上がって、また明日からがんばろうって思ってくれたら最高。引用元:
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』パンフレット P25
もともと『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』を観ても、感想を書いたり、誰かに話すつもりはなかったんだけどさ。
というのも『幕が上がる』っていう、ももクロが以前主演した映画や舞台作品で、新書相当40,50ページ分ぐらいの感想を書いたことがあって。
俺が。好きだから。ももクロが。
そんで、またももクロの舞台作品が出てきたからって同じことをやったら、そのジャンルを監視してる、芸術に一家言あるやつみたいになるし、キモいじゃん。
俺も自覚と節度はあるんだ。
でも、ももクロのファンとしての基本方針の一つに、
「メンバーにお願いされたことには従う」
というのがある。
あーりんが「思ったことや感じたこと」を「わいわい話して盛り上がってほしい」と呼びかけた以上、そうしたい。
俺が人にキモいと思われるかどうかなんて、もはや些末な問題になった。
唾棄する。
が、しかし。
俺にももクロの話ができる友達はいない(理由:性格に問題があるので)
Twitterに書こうにも、獣姦にも劣るとされるネタバレという禁忌を衆目に晒すことになるし、2ちゃんのネタバレ感想スレに名無しで書くにしても、おそらく文章量的に「荒らし」になる。
なので、ブログを選ぶことにした。
こうやって、気心の知れた友人相手にファミレスや居酒屋で語る口調で、だらっだらと『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の感想を書こうと思う。
話を聞いてくれるお前のことは、こう設定する。
まず、ももクロに興味のない、外野の人間である。
しかし、俺がいかなるADHD崩れであるかをよく知っていて、どれだけ長時間かつ独りよがりなジャーゴンを駆使されても、何ら文句を言わない(=自我の薄弱な)友だちだ。
ないし、そんな存在を"ブログ"が担っていると言えるのかもしれない。
俺はももクロのライブやイベント、あらゆる文物の感想というものは、人に話す・話さないにかかわらず、いつもEvernoteにダラダラ書き留めている人間なんだけどさ(ブログにたまに載せているのは全体の5%にも満たない)。
『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』については、そんなチラシの裏を、他人が読んで分かる程度に書き起こしてみようと思う。
まあ、人間って、あらゆる生物のうち、言語を特質とした生き物じゃないか。
だから、ヒトは思ったことを言葉にしないと健康を害するようにできている。
ラカンが言うように、言葉とは、赤子が母の乳房から引き剥がされる代わりに与えられる、おしゃぶりのようなものだ。
その程度の戯れでダラダラと感想を語りたい。
それに、ももクロの楽曲では、"言葉に対する勇気"がさまざまに歌われている。
『走れ!』 −キミの前じゃ素直でいたいんだ
『労働讃歌』 −難しいことは掘り下げないとわかんないんだけどね
『Re:Story』 −あるだけの言葉をもってして君と話してたいんだ
こんな精神で、思ったことを思ったままに、全部語る。
長くなる。
ごめんね、ありがとうって。
これも『笑一笑』っていう曲の歌詞なんだけど。
■オーバービュー
まずは、そもそもこの舞台ってどういう作品なんだよってところからだよな。
この舞台の形態は、ジュークボックス・ミュージカルと言って。
つまり、世間に元から流通している歌謡曲を劇中で歌うミュージカルのことなんだけど(わかりやすいのは『マンマ・ミーア!』)、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』では、ももクロがももクロ自身の曲を使い、それを行う。
ももクロって4人組のグループでさ。
この舞台では、とある高校のダンス部の4人として現れるんだ。
4人はダンス部の立ち上げメンバーなんだけど、部室も与えられないまま日々練習に励み、高校2年にして、なんと全国のダンスコンクール決勝へ勝ち上がることになった。
で、コンクール前日、渋谷区の交差点で、いよいよ明日だね〜〜〜!!と4人が盛り上がって、思わずその場で練習しはじめる。
すると、交通事故にあい、全員死亡する。
(この死ぬくだりを、こないだ紫担当の高城れにという子がラジオ番組で「ちょっとしたアクシデントで」と説明してて笑った)
彼女らは生まれ変わる。
が、一人だけ、ダンス部のリーダーであるカナコ(百田夏菜子っていうももクロのリーダー且つ、赤担当のお方が演じてらっしゃる。この作品、全員、実際の下の名前を役名に使っている)は、死を理解できず天界を浮遊するんだ。
カナコが転生を拒否したまま、霊魂として他3人のもとを経巡り、また再び4人でダンスをしようとするファンタジー作品であると。
この『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』は。
タイトル『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』はその誘い文句であり、同時に本作のキーとなる楽曲名でもある。
表題曲『Do You Want to Dance?』だけ、ももクロの内製物じゃなくて、外部から供給している。
Bobby Freemanによって作られた、50年代アメリカの雰囲気をよくよく表現したロックのクラシックナンバーなんだけど、映画『アメリカン・グラフィティ』に挿入歌として使われている。
(個人的にはロジャー・コーマンの最高傑作『ロックンロール・ハイスクール』で、カメオ出演したラモーンズが歌う場面のほうこそ思い出深いけど)
『アメリカン・グラフィティ』自体が、50年代後半〜60年代前半の古き善きアメリカを象徴するナンバーを流しまくる、ジュークボックスのような映画になってるんだよね。
たとえば、『アメリカン・グラフィティ』の影響下で撮られた『グリース』は、ピンク担当、あーりんの2018年ソロコンサートの世界観に援用されたし、『アメリカン・グラフィティ』に登場した伝説的ラジオDJ、ウルフ・ジャックマンは、その影響力から日本に小林克也およびスネークマンショーを生み出した。
小林克也とは、ももクロが毎年バレンタインにやっているイベントの直近回で共演していてさ。
小林克也がももクロにウルフ・ジャックマンのDJ精神を伝授していたりする。
ももクロとの遠縁な関係はこんなところか。
で、『Do You Want to Dance?』に戻ると。
この曲のポイントは、まったくメッセージ性などないということだと思う。
女の子をダンスに誘う甘ったるいナンパ文句を3パターンほどリピートするだけ。
日本の文化で喩えれば、「キミ、カワウィーネー」ぐらいのことしか言っていない
Do you want to dance and hold my hand?
Tell me baby I'm your lover man
ダンスしよう ぼくの手を取ってさ
聞かせてよベイビー 恋人はぼくだってWell do you want to dance under the moonlight?
Squeeze me baby all through the night
月明かりの下で踊ろう
キミを夜通しギュッと抱きしめるからDo you do you do you do you want to dance
キミキミキミキミ ダンスしようよ
Do you do you do you do you want to dance
キミキミキミキミ ダンスしようよ
Do you do you do you do you want to dance
キミキミキミキミ ダンスしようよ
見ての通り、ただキミとダンスがしたい!という指向性だけが示されている偏差値5の楽曲だ。
死んで天界を浮遊するカナコは、幸せの絶頂にいたあの仲間たちとまた踊りたい。
その気持ちを表明する曲で、『Do You Want to Dance?』は舞台の節々で歌われ、踊る。
(俺は『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』を観るたび、シナリオや時系列をExcelに整理してるんだけど、そこで数える限り、8回歌われてるな)
同時にこの曲は「幸せだったあのころ」を象徴している。
『アメリカン・グラフィティ』の場合、当時冷戦やベトナム戦争でアメリカは国家不信に陥っていた。そんで、かつて50年代のアメリカはただただ楽天的で幸せだったなーということを、アイロニカルに振り返る構造の映画になっている。
楽天的な楽曲だけど、楽曲と自分との間には、アメグラなら<ベトナム戦争>、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』では<交通事故>といった「死」の切断線が引かれている。
単純にブギウギイエイ!な曲ではない。
この曲をビーチボーイズやラモーンズがカバーするときもだいたいそう。
「楽天性への再帰」として歌われる。
だから、舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』で、楽曲『Do You Want to Dance?』を「<幸せだったあのころ=前世>を取り戻そう」というメッセージ媒体として用いるのは、アメリカ本国の流儀をちゃんと踏襲していると言える。
話の本筋に進むと、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』は、作品の冒頭、ダンス部の4人はすでに完成された幸せの絶頂期にいる(ふつうの青春ドラマならここがクライマックスになる)。
それが、開始2〜3分で、たちまち死によって打ち切られる。
驚くべきは、アイドルのミュージカルなのに「希望に満ちた世界を生きていても、物質として壊れたら全部おしまい」という事実を見せつけるところから始まるのが、『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』の特色なんだ(いざ字に起こすとひどいね)
魂として天界をさまようカナコは、また4人で集まりダンスがしたい!という強烈な欲望を持っている。
しかし、転生を拒み、肉体を持たずにいる以上、現実世界において再びその願いを実現させることはできない。
だから、カナコは<非現実としての夢>の世界を仮構し、そこに他3人を呼び込んだのち、<欲望としての夢>を実現しようとする。
見ての通り、それなりに倒錯的なことを試みている。
だから、何らかの事由をもって現実から引き剥がされた者たちにとって、「夢はいかにしか可能か?」という問題と格闘する物語になっていると思う。
ここまで語っておいて何だけど、作品自体は、至って明るい。
たとえば宮崎駿のアニメ作品も、つねに死を重要なファクターに据えつつ、子どもたちの鑑賞に耐えうるように。
この舞台『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?』も、ついこないだ、子どもが泣いたり大声を挙げたりしてもOKなファミリーデー公演が設けられ、終演後には、子どもたちがドゥユドゥユドゥユドゥユワーナダーンス?ってロビーや帰り道で踊っていたという話があるぐらいなんだよね。
作品のざっくりした輪郭はそんなところか。
【NY】ももいろクローバーZ 「アメリカ横断ウルトラライブ」感想(4/4)
11/19
NYでは朝から昼過ぎにかけて、MOMAに行き、長年書籍でよく慣れ親しんできた近代美術の数々を生で鑑賞した。
下記のツイートにある現地の人たちの感動を、俺は美術で味わってきた。
現地の人の話で1番心に残ったのは、ずっと円盤とかを見ててやって欲しいって思ってた曲をやってくれるのは1つずつ夢が叶うのと同じ感覚なんだって話。
— りょう (@ryomcz) 2016年11月19日
会場のプレイステーションシアターには、14:30ごろから並び始めた。
開場すると、空港の搭乗時よりも厳しいセキュリティチェックが行われる。
俺の前の女性は、リュックの中の化粧ポーチからメガネケースまで中身を開けてチェックされていたし、セキュリティのスタッフはモバイルバッテリーを手にこれは何だ?安全と判断して良いのか?と数秒フリーズしていた。それぐらい一点一点を吟味している。
(でもモバイルバッテリーの存在は知ってろよと思った)
巨大ビルを飛行機2機で破壊された都市の荷物チェックは、ノコギリで襲われた日本のアイドル業界のそれとは綿密さが違う。
長い荷物チェックの並びを抜け、フロアに入ると、アリーナに相当する最前スペースが5列分ぐらいまで埋まっていた。
その後ろにある二段目のフロアがガラ空きだったので、そこの最前中央を取った。
ステージとほぼ同じ高さで、何にもさえぎられず、まっすぐパフォーマンスを見ることができる。
遅く並んだ割には、かなり良い位置が取れたと思う。
後になって知るが、この場所は上下左右すべてにおいて中心部なので、ステージ上のメンバーが会場中央に目を配るとき、「うわっ、こっち見てる!」という錯覚を毎分味わえる。
VIPイベントの写真撮影時、この日も三度目の幸運に恵まれた。
撮影の自ブロックにおいて、最前列のうちの一人になった。
壇上に上げられる前に、あー、嬉しいなぁと思っていると、ほかのファン同士が推しの真後ろに行けるよう急いで位置交換を行っていた。
あーりんは奥から2番目なので、れにちゃん推しの人が、しおりん推しの人が、夏菜子推しの人がバトン渡しのように俺を前へ前へと通してくれた。
壇上に並び終わり、一番前にメンバーが座るとあーりんは俺のやや斜め前になった。
こんな具合。
黒が俺で、濃いグレーが後で話に出てくる夏菜子推しの人。
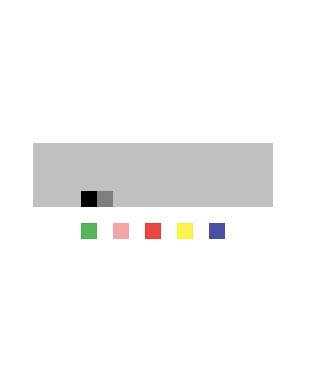
俺を気遣い、奥に回してくれた夏菜子推しの彼のほうがあーりんに近い位置になった。
彼が俺に、すみません!と言う。
いやいやいやいやいやいや、これでも十分幸せですよ!と言ったら(50cm先の有安さんのうなじの美しさに見とれていたし)、彼が前を向いて「あーりん!」と叫んだ。
最前にいるあーりんがパッとこちらを振り向く。
夏菜子推しの彼は、ここにあーりん推しがいるよと俺を指差す。
あーりんが俺を見て、なーにー?と聞いてきた。
ここまで2秒ほどの出来事である。
幸運はつねに試練の形で与えられる。
あーりんに何て答える?
いや、というか、もうあーりんが俺を見ている。
フリーズするぐらいなら何でもいいから何か言わなければ!!!
と0.5秒で思い詰めた自分が発した言葉には、自分自身、驚いた。
「どうも!」
あーりん「なにが!?笑」
俺は年内をめどに死んだほうがいいな、と思いつつ、しかし反省している暇はない。
慌てて頭を仕切り直し、本当に言いたいことは何だろうと考え、「何があっても一生ファンでいます!」と言った。
撮影が控えているので、あーりんは前に向き直しながら、「あはは!うれし〜」と言った。
最後、お見送りで並ぶメンバーの前を、一列ずつ壇上の客たちがはけるときに、あーりんの前を通ると、あーりんが俺のことを覚えていてくれたのか、あっ、と気づいた顔をして、あらためて「ありがとね〜♪」と手を振ってくれた。
舞台袖にはけた瞬間、夏菜子推しの彼に、腰が鋭角になるほど頭を下げ、ありがとうございます!!!と礼を言った。
前後にいた他のあーりん推しの人たちも、やったじゃないですか!!と興奮気味にハイタッチを求めてきてくれた。
こんなに素朴にキラキラしたファン同士の交流をするのは初めてだった。
(恥ずかしいので、いつか彼らと別の現場で再会したら、申し訳ないけど死んでもらおう)
たった数分であれ、あーりんが俺の顔を覚え、俺のことを気にかけてくれた。
真面目に言うが、俺はもう一生ライブやイベントでの席運、つまり"近さ"に恵まれなくてもいい。
何ならチケットにまったく当たらない呪いにかかっても、そんなことはももクロのファンをやめる理由に何ら値しない。
元から一生ももクロのファンでいると自分の中で誓いを立てているが、それをあーりんに明言した。
俺はあーりんより14歳年上だから、あーりんが80歳になったとき、94歳のファンでいよう。
いつか遠い遠い未来、あーりんが天国に召されるとき、マホロバケーションのMVにある天界のライブ会場で、ピンク色の魂の一つとして先入りし、開演時間を待ちわびていよう。
以上は自慢話だろうが、しかし書いた意義を説明したい。
形態はどうであれ、俺に限らずメンバーの姿形を真近で見て、ときに言葉を交わし、多幸感に包まれたファンはたくさんいる。
たとえばアメリカの人たちは、OVERTUREの練習会を終えて、壇上から降りるとき、メンバーにハイタッチのお見送りをしてもらっている。
ファンが感涙を流す場面は、会場ごとに何度も繰り返された。
この撮影会では俺だけが特別な思いをしたのではない。
それだけ神イベ(アイドル業界用語)だったのだ。
この多幸感に包まれた観客たちが、VIPイベントを終え、1時間先に控えているライブに臨むとき、自分たちは命を捧げるように今日を楽しもうと心に誓う。
その素地は、これまでのライブ本編を、一般チケットで入ってきた人たちも歓喜の渦に巻き込む空間にしていったことに大いに作用している。
プレステシアターの一般入場が開始しても、例のセキュリティチェックのおかげで少しずつしか人が入ってこない。
それでもわかるのは、ニューヨークの一般チケットは、本当にももクロを知らない、あるいは名前しか知らないレベルの人がかなり多くいる。
服装や立ち振る舞いが、見るからにふつうの、オシャレで遊び慣れしてそうなニューヨーカーたちなのだ。
VIPイベント終了したけど(天国だった…)、川上マネージャー曰く、ハワイとLAの口コミを受け、終盤追い上げのチケット売り上げにつながったようでNYが全3回のうち一番の客数に達したとのこと
— demio (@ganko_na_yogore) 2016年11月20日
VIPイベントの終わりに川上マネージャーから説明された通り、VIP320枚に対し、一般は700枚売れたと言う。
おそらくハワイもLAも、一般入場よりVIPのほうが多かったと思うが、NYは一般がVIPの2倍にまで上回った。
ハワイとLAで"ヤラれてしまった"アメリカ人たちの口コミの力とスピードはおそろしい。
最低限通路にすべきスペースを残すと、プレステシアターのフロアはほぼ満員になった。
ハワイやLAと同じく、これまでどおりパフォーマンスをすれば、初見の人たちでも何ら問題なく楽しませられることは確信していた。
場所によって手の抜き方を考えるようなグループでないことは知っている。
それでも、他の2会場に比べて、すでにももクロの楽しみ方を知っている人とそうでない人の比率において、NYは後者に寄っている。
ハワイが熱狂と叫びの空間で、LAが幸福に満ちたラウンジだったとしたら、NYは最後に来て"挑戦"だった気がする。
開演時間の8時を過ぎても、現地の人たちがライブに臨むためのグッズを買おうとしている(嬉しいじゃないかさ)のを待つと、ずいぶん遅れての開演になった。
『さくらさくら』の舞いから始まり、『夢の浮世に咲いてみな』『MOON PRIDE』の冒頭曲を聴いているとき、ふとホノルル空港に降り立ってからいままでが随分長い道のりのように思えてきた(思えばずっとせわしなく動き回ってきた)。
アメリカツアーで聴けるこの奇跡のような『夢の浮世』も『MOON PRIDE』も、もうこれが最後なんだ、と思うと、VIPイベントでの多幸感も入り混じり、涙が出てきた。
ニューヨーカーたちは、会場内のただならぬ盛り上がりに、なんだこれは?と初めは驚いた様子だったが、やはり文化的に洗練された人たちだからか、初めてのアイドルライブを楽しもうと順応に努めていることが見て分かる。
初見の彼らはコールなど入れようがないが、ノリノリに体を揺らしていたり、キャッハーと笑顔だったり、なんだこれは?楽しいぞ!となっている様子が二段目のフロア最前からよく見渡せる。
この客席を目にできることも、ツアーに参加した大きなバリューだと思った。
アンコールになり、田中将大の応援曲『My Dear Fellow』が歌われた後、矢継ぎ早に怪盗少女につなげられたとき、会場全体が"プッツン"した気がする。
ニューヨーカーとももクロの既存ファンたちが溶融し、ハワイやLAと何ら遜色ないレベルの歓声やコールが沸き起こった。
続く『ニッポン笑顔百景』でアンコールが締めくくられたとき、これで終わりだと思ったニューヨーカーたちが出口に向かい始める。
しかし、ダブルアンコールが響き出した瞬間、多くのニューヨーカーがフロアに戻り、最後の一曲を見届けることを選んだ。
メンバーがダブルアンコールに応じて現れたとき、夏菜子が「また来年もここに来れるよう、私たちはこれからも駆け抜けていきます。その思いを込めて…『走れ!』」と(俺の記憶では)言った。
4月にこのアメリカツアーが発表されたとき、企画のコンセプトは正直よく分からなかった。
というか、おそらく運営側もそんなにカチッと考えていない気がして、ファンがブラックボックスの中身を考えるのはくだらないと思っていた。
俺はただ盲目的なファンの一人として、単に「やるなら行こう」と思った。
このライブがアメリカ横断ウルトラクイズの様式を踏襲しているとおり、ももクロをアメリカ進出させるというよりも、日本人をアメリカに連れて行くイベントだと川上マネージャーも何かの折に発言していた。
つまり、ある種、日本人による内向的なアメリカ旅行付きのライブであると。
しかし、ハワイ、LA、NYを回って実感させられたのは、日本人たちが思う以上に世界はももクロに開かれている、ということだった。
『走れ!』が歌い終わったとき、すべてやりきった感に包まれた。
これでアメリカツアーは完全に終わった。
客出しのBGMが『あの空へ向かって』から別の音楽に変わった後も、「世界のももクロNo.1」コールが継続している。
ももクロはおそらく、夏菜子や川上マネージャーが示唆したとおり、来年もアメリカでライブを行うだろう。
もっと長い目で見れば、ヨーロッパツアー、アジアツアーもいずれ行うと思う。
たとえば2015年に福岡ヤフオクドームでライブをした翌年には、ドームトレック2016で全国のドーム・スタジアムを回ったように。
このアメリカツアーは、これから先の展開を自ずと予感させられる形の成功を収めた。
それはどの都市で何人動員したといった量の問題ではない。
行く先々の都市でアメリカの人々に聖痕を刻み込んだ、という質的な意味で成功を収めている。
それを見届けることができた。
また次も行こうと思う。
NYのライブが終わったとき、会場内に寂寥の念は感じられなかった。
終わったのでなく、ここからが始まりだという兆候的な予感に満ちていたことを、ありありと思い出す。
【LA】ももいろクローバーZ 「アメリカ横断ウルトラライブ」感想(3/4)
アメリカツアー三箇所とも演出・セットリストに大きな違いはない以上(※)、ハワイの感想が大枠をすでに果たしている。
LAとNYは、差分を主に語る。
※今回の演出・セットリストが練りに練り上げられた解であることは、ハワイの感想に書いたとおりよくよく実感している。回ごとの大差はないことは必然的である。
===
11/17 LAでは、朝早くから会場のWilternに並ぶことにした。
(といっても、朝8時から並び出してすでに40番目ぐらいだったときは食欲を失った)
理由は以下のとおりだ。
・LAの行きたい観光スポット(ゲッティセンターとハンティントンライブラリー)はどれも距離が遠く、時間消費が激しい
・LAは温暖気候なので、長時間動かなくてもそれほどつらくならない
・三箇所のうち、一つぐらいは「前のほうで見る」を体験しておきたい
並んでみて実感したのは、アメリカの人たちは「ライブ会場に並ぶ」ことのルール付けがけっこう緩い。
チケット種別であるgeneral admissionをGoogleで調べた時点で知っていたことだが、アメリカは整理券を配るという文化があまりなく、ライブなどで良い位置を取りたければ好きなだけ早く並べばよい、といった考えが基本にあるらしい。
人気公演なら10時間待ちする人など、まあいるだろうね、のレベルだという。
また、日本では並び方一つで近隣施設からクレームが来るが(それはしかるべきクレームだと思うが)、アメリカでは道や出入口を完全に塞ぐなど、あきらかに実害的でない限り、あまり誰も文句を言ってこない。
事実、早くから並んでいるLAの人達はけっこう大きい木製の長椅子を持ってきているし、並んでいる人たちが一箇所に集まり歓談し、歩道の半分ぐらいを塞いでも、いまだ誰それと揉め出す気配はない。
(俺が気づいていないだけかもしれないけど、目立つレベルのことはなかったはず)
俺も14時になりホテル(会場から徒歩1分)のチェックイン時間になったときや、飲み物を買いに行くときには、ちょくちょく席を外す程度の緩さで行列に参加した。
(みんな、ここは誰それの場所だと互いに覚えあっている)
俺は基本的にモノノフとの横つながりは作らない人間だが、たまに会場や行列で隣の人に話しかけられれば、礼節をもって明るく世間話ぐらいする。
LAでは特に行列中、いろんな人が自分の並び位置を離れて話しかけてくる。
行列が一種の社交空間になっていた。
ファン同士による食べ物の差し入れや自作グッズの配布も回数がとても多い。
この社交性は、ハワイとはあきらかに違う部分だと思った。
れにちゃん推しのおじさんに話しかけられ、彼に聞いた話では、前日50人ほどの現地のももクロファンによるオフ会が開かれたらしい。
現地人のもよおしといっても、コネクションさえあれば、日本からやってきた人もどうじょどうじょと招かれる場だったという。
(そのおじさんも参加したそうだ)
前日のオフ会で会った人たちが、翌朝Wilternの行列で、やあやあ、と再び顔合わせする。
いわばオフ会のリレーションがそのまま移植されたのが行列の社交空間だった。
(と話を聞いて理解した)
ポカポカした気温と、たまに人に話しかけられるおかげで、開場までの8時間をそんなに長くは感じなかった。
LAでは、開場後、VIPイベントの写真撮影タイムにおいて、脳が溶けるような幸運に恵まれた。
Twitterに一度書いて、品性に欠けると思いすぐ消したが、ブログくんだりまで見に来るやつには何を書いてもいいと思うので、もう一度ここに記す。
写真撮影で50〜60人ごとのグループに分けられるとき、目の前で、はい、いったんここまでと俺のところで切られ、自ずと次の自ブロックの一人目になった。
誘導された位置はこんな具合だった。
メンバーが全員1m以内にいる。
かつ撮影のグループ全員が整列を終えるまで、ずっとメンバーはこの位置にいる。
近いし、長い。
ふだんのライブと比較すれば、顕微鏡で覗いているように感じる。
予期せぬ位置への誘導とメンバーの近さにより、俺は完全にこの位置で驚いた顔をしていた。
れにちゃんが手を振ってくれた。
振り返すと、れにちゃんは俺の驚いた顔に苦笑した。
あーりんに手を振ってみた。
振り返してくれた。
あーりんにも同様に苦笑された。
恐ろしいことに気づいた。
この距離ではメンバーに手を振ったりした場合、ほぼ確実に何らかの反応をしてもらえる。
メンバーのパーソナルスペースに漸近しているため、彼女らにとってスルーできる距離ではないのだ。
ふだんこちらがライブ中、イベント中にメンバー名を叫んだり手を振るとき、それはあくまでも存在肯定の身振り手振りであり、そこにキャッチボール性は期待していない。
だからこそ、一方的に好きなだけ手を振っていいし、名前を叫んでもいい。
しかし、ここでは勝手が違う。
メンバーがしっかり反応してくれるから、俺が好きなだけ手を振ったり話しかけたりすれば、それだけメンバーの時間を奪い、果てはイベントの進行を妨げる。
なんていうことだ…。
ここではファンとしての身振り手振りに責任が生じる。
("責任"だけ背景に岩文字で)
そう思った時点で動けなくなった。
何ならジロジロ見つめるだけでも、怖がらせてしまいそうだ…と思った。
じゃあ、どうすればいい?
アイドルを前に悠然とすればいいのか?
憧れのアイドルを前にして悠然とするファンって何だ?
それも違くないか?
何か模範例はないか?
ももクロ以外のアイドルの握手会などで、憧れのアイドルにフランクに笑顔で話しかけるファンの姿を思い浮かべた。
あれも実はダウンタウンと共演する芸人たちみたいに、はつらつとしているように見えて裏ではゲロを吐くぐらい緊張しているのかもしれない。
一種の強さとして、アイドルと相対するとき、笑顔でいるのかもしれない。
そう考え、笑顔にした。
あれ?
しっくりきた気がする。
なるほど、こうか!!!!!!!!!!!
人は極限に立たされたとき、1分間で成長できる。
いつかこの日を思い出してきっと泣いてしまう。
LAのライブの盛り上がりは、相変わらず凄まじいものだった。
横から見た場合の会場の作りは、だいたいこんな形だった。
二階席がある。
一階席は(この規模の会場では本来使わない言葉だが)深く沈んだアリーナと、階段状になったスタンドがある。
こうしたRepublikとは異なった階層的な会場の作り、さらにそもそもステージがけっこう高めなことにより、ステージ上のメンバーが見れない人はそんなに発生してない(と思う)。
ハワイで発生した圧縮は、LAでは起きなかった。
ファンたちはメンバーを視認することさえできれば、前へ前へ押し寄せることはない。
また、Wilternは天井が高いため、人の体温によって会場内が蒸れて、すえた空気になることもない。
Republikにあった野生的な熱狂は、あの建物の作りも大きく関係していたことに気付かされた。
だからといってLAのライブの盛り上がりは、ハワイに見劣るものではない。
ギラついたスラム感だけが抜けていると言えばいいだろうか。
さらにLAは先述のとおり、客同士のリレーションがかなり高度に構築されている。
ハワイでの盛り上がりはそのままに、この会場内が国籍を問わず、まったく一つの幸福圏であるような柔らかみがあった。
ダブアンまで終わったとき、外国人たちは歓喜の声を上げ、自分たちはとんでもないものを見たという驚きに包まれた顔をしている。
俺の近くにいた現地の人は、モモカー!!!!!モモカー!!!!!と目を見開いて繰り返し咆哮していた。
この幸福感と驚き(情報処理が追いつかない)がないまぜになった彼らの様子に、既視感を覚えた。
Twitterにも書いたことだが、2011〜2012年ごろ、ももクロのライブやDVDを見た人たちがかかった熱病に近い。
なんか2011〜12年あたりの、ももクロのDVDあるいはライブを見た人たちがみんな「ヤバいものを見た」と眩暈にかかってハマっていってたときの高揚と近いものを外国人たちのリアクションに感じる
— demio (@ganko_na_yogore) 2016年11月18日
ここにいる現地人の彼らは、次またアメリカでライブをやるなら、万難を排して来るだろう。
またそのとき、身近な"感染者"を引き連れてくるだろう。
そんな楽観的なことを抵抗なく考えてしまうのは、「この高揚」の次に何が起きるのか、を過去すでに経験して知っているからだ。
===
最後に些細なことだけど、地味に驚いたことが一つある。
『キミノアト』の歌い方が音源寄りに戻った。
ハワイでは、
旅立つたぁ↑めにぃ↓
無理にかくぅ↑したぁ↓
というこぶしの入った歌い方がされていたけど、LAをもって(次のNYでも)フラットな音源寄りの歌い方に、数年ぶりに戻っていた。
一部の人はキミノアトのこぶしの入った歌い方を忌み嫌っているが、俺はそれほど気にならない。
歌い方がむかしに戻ったことに、単純に「へー」と思ったので、ここに書いたまでと強調しておく。
(ずっと音源を親しんできた現地の人たち向けに、ツアー中に限り音源寄りの歌い方を選んだ、という可能性もあると思う)




